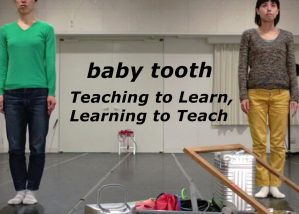
アートユニット「乳歯」とは、振付家・ダンサーの神村恵と美術家の津田道子による2人組の修行ユニットで、身体、映像、言葉などの複数のメディアを駆使して、これまで当たり前とされていることを問い直すパフォーマンス作品を制作・発表してきました。京都の暑い夏2025ダンスワークショップのプログラムとして「学ぶを教わる/教わるを学ぶ」ワークショップが開催された。日頃見逃しがちな「当たり前のこと」を問い直すようなワークが展開されました。8月14日から17日の4日間にわたって開催されたワークショップの体験記です。
Contents
初日:「休む」—物を休ませるという挑戦
初日は神村恵さんのワークでテーマは「休む」でした。参加者全員で「物を休ませる」ことに挑戦しました。今回は人ではなく「物」が対象でした。会場にあった机や椅子などを参加者が思い思いに選び、それぞれの解釈でそれらを休ませることを試みました。
室内に置かれている道具たちは、何らかの目的を持ってデザインされています。それらの道具を休ませ、仕事から解放するということは、その目的を一時的に消去し、道具としての機能を停止させることに注目が集まりました。
多くの参加者は以下の2つのアプローチを選択しました:
- 物語的解決法:道具の目的を物語として捉え、それを物語として解決する
- 視覚的解決法:テンションがかかっていそうな部分を横に倒すなど、見た目上の目的を解放する
物語的・視覚的アプローチは極端に分岐するものではなく、両方を多分に含んだ表現として現れました。中でも興味深い意見も出てきました。あるチームは非常口マークの緑色の人が戸から走り出るロゴマークに向かって「もう走らなくていいんだよ」と声をかけるもので、それは「物が持っている時間にこちらが歩み寄って沿わせてあげること」と述べられました。この方法論は、具体的な行為ではなく、人間が作った道具たちと同等の目線に立ち、寄り添う形でそのこと自体が休みもしくは癒しという形で現れる画期的な視点でした。
考えてみると、もし会場が森の中であった場合、人間によってデザインされたものは一つもないことになります。その場合、そのものが持っている時間やありさまに沿わせてあげることでしか休ませる方法はなく、そもそも「休ませる」という概念自体が存在しないのです。
森のような場所では、植物であれば光に向かって伸びるなどの生の方向性がありますが、無機物の石の場合は方向性がなく、「尖っている」や「顔に似ている」といった形が人間にとっての意味として解釈される可能性があるのみです。
私は以前、スタジオイマイチ10周年の際、当時注目されていた働き方改革とともに「休み方改革」も必要ではないかという疑問から、休み方改革のワークショップをメンバーで開催した経験があります。そのワークショップでは幅広い年齢層の参加者と共に、休みの日の過ごし方や「休み」とは何かについて話し合い、最終的には隣の人に(かなり無責任な形ではありましたが)休み方のプランを組み立てて提案するという内容でした。このワークショップでも最終的に「働くために休んでいるのか、休むために働いているのか」が分からなくなり、そもそも目的を持って行動すること自体が疑わしくなる問題が立ち現れました。
2018年10月21日”10年後の休み方は?〜休み方ハッカソン!〜”
ゲストファシリテーター 西翼
2日目:津田道子とランナーの視点
2日目は津田道子さんのワークでした。彼女はコロナ以降にマラソンを始め、今では定期的にトライアスロンなどの大会に参加するアスリートです。その経験が作品にも反映され、初心者向けの走るトレーニングが行われました。
まずは姿勢を意識し、「走る」ことを意識するのではなく、倒れる体を支えるように足を前に出しながら進む訓練を行いました。
続いて「ドリル」と呼ばれる特定の動きやスキルを習得するための反復練習では、自分の苦手とする動きを歩きや走りの中に組み込み、シンプルな反復運動として行うことでトレーニングとして扱います。走り方に注意を払い、これまでどのように走ってきたかを振り返り、よりよく走るために改善を試みるものでした。
最終的には自分のためのドリルを制作・発表し、参加者全員でそれを試すというものです。
このエクササイズはダンスに近いものがあり、それぞれの課題に対するトレーニングメニューを自分で作ります。多くの参加者は自分自身を見つめ直し、足りない部分をどのように強化していくかというメニューを考え、それを発表し、みんなで実践しました。
私の経験では、特にカニングハムのテクニックはバレエのようなしなやかさは求められていないため、素早く筋肉を動かすことが重視されます。バレエでいう足のポジション5番はなく、胸の真ん中にも関節点があるので、背中を丸くするようなポジションがあるのが特徴です。低速でゆっくり動かすことに従事しており、スポーツのトレーニングに近いものだったのだとこの時気付かされました。
マースカニングハムのドリル
初級はもう少し簡単
3日目:痕跡を読み取る不思議なワーク
3日目はかなり不思議なワークでした。
前半は、部屋に何らかの行為を施す「犯人」のような作業を行い、次にそれらの活動を一切知らない「探偵」的な役割の人が、その部屋で何が行われたかを言い当てるというものでした。一見変わっていない部屋の中に残る気配や痕跡を読み取り、過去に行われた行為の可能性を想像する。そして、その想像する姿をみんなで見ることが重要視されました。
後半では、やることを先に述べてからその行動を行うというものでした。簡単に言えば、子供がトイレに行く時に親に「トイレに行きます」と言ってから行くようなものに近く、言葉にすることによって、その所作を実行している最中の体験が大きく変わります。
言葉に変換すると世界の見方が変わるということは実際にあるのですが、その言葉がある種の呪いのように働き、自分が述べた運命にどのようにはまっていくか、それを観察するところが特徴的でした。
4日目:見つめ合いとセンターワーク
見つめ合いワーク:
2組が1m間隔で向かい合い、目を合わせてじっと見つめ合うことを2人ずつで行い、1分ごとにパートナーを変えて行いました。真正面で恋人でもない人と見つめ合うことは少ないため、照れ隠しで笑う人も多く見られました。この笑いは恥ずかしさから自分を守るバリアとして働くことが多いようです。
次に歩き回りながら、目があった人と目を見つめ合うワークが行われました。
日野晃という古武道家のワークに「正中線を合わせる」というものがあり、剣道などで行われるものですが、自分の中心と相手の立ち姿の中心を重ねるというワークです。フェンシングやボクシングなどの西洋を中心とした武道では弱点にもなりうる自分の中心をわざと合わせるという日本的な思想のワークです。中心といっても人の顔は左右で必ず違っており、鼻や顎が歪んでいたり、立ち姿も歪んでいるので、正確なシンメトリーのラインが真ん中にあるわけではありません。しかし、合わせてみると、ピタッとくるところがあります。
日野晃の場合、センターを取るところで「目を見て正中線を取る」ワークは終わりますが、乳歯のワークショップではその後どんな感触になるかも体験しました。次第に立って動き回れるようになり、歩き回りながらランダムに目線を合わせてじっと見つめ合うワークに移行しました。
目が合えば、遠くでも近くでもそのワークは行われます。私の場合、部屋の対角まで遠ざかることができ、見つめ合っている間に別の人が横切っても継続することができました。この長距離での向かい合わせができた際は、2人とも「ここまでできた」という驚きがあり、「この辺だろう」というところで2人が同時にクスッと笑いました。
余談ですが、この場合の笑いは自身の感情を隠すための防衛機制としての笑いではなく、終了したことによるコミュニケーションとしての笑いでした。E.ゴフマンは日常的に何かを演じることで防衛機制をしたりコミュニケーションを円滑にしたりすることを考察しましたが、この見つめ合いと笑い(にやけ)にはその深層部分でのやり取りが見えるワークとも言えます。
空間描写のワーク
最後に行ったのは絵を描くことでした。空間の中にいる自分が対象物(今度は人ではなく物)に向き合った時にどうなるか、そしてその様子を記録し、自分がどのようにそこに関わるかを絵(スコア)として記述するというものです。空間の向きや自分も含めたその景色を記述することが求められました。
参加者の表現は多様でした:
- 広い空間の中にポツンと自分が描かれているもの
- 光の方に向かって進んでいくイメージを提示するもの
- 全てのものには心臓のようなものがあり、それに向き合うことができるとして、描くものに心臓のような軸を描いているもの
- 空間を表現できずに感覚を重視し、抽象的に感じたものをキャラクター化して描くもの
多くの人がスケッチしたものでも記憶したものでもなく、体験後に別の部屋で描いたにも関わらず、どの場所にどんなものがあったかという細かいディテールを書き込んでおり、驚くほど精密に記憶していることに感銘を受けました。
私事ばかりで恐縮ですが、4月に山口の旧山口支庁を題材に制作したビデオ作品が、これまで市役所として長い間使われていた建物から受ける印象をどのように自身の身体を通してマッピングするかという主題だったことから、アプローチはやや違いますが、多くの部分が交差するワークでした。
この4日間を通じて、「休む」「走る」「観察する」「マッピング」など、「学ぶを教わる/教わるを学ぶ」とはあまり関係がなかったが、一見異なるワークが、「どのようにものを見て、どのように関わるか」という点で全体を緩やかに貫く共通のテーマがあり、新しい感覚を見つけるために充実した4日間だったのではないでしょうか。