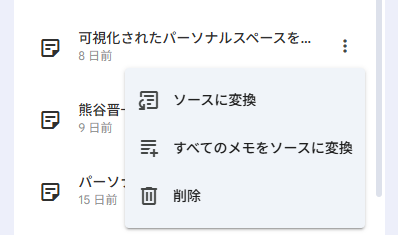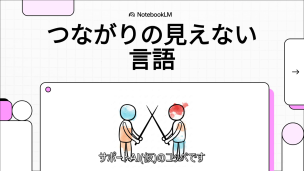
今回は、ほとんどタイプしないで論文を書く方法を説明します。そもそも私は作文が苦手で、ほとんどタイプしません。タイプしても誤字脱字が多すぎて、小学生の頃から国語はオールFでした。実際、ちゃんと書けているのか自分では本当のところ判断できないのですが(笑)。
今回は、「パーソナルスペース再発見」の紹介を例に解説していきます。
>>今回使用のhttps://notebookLM「パーソナルスペース再発見」
Contents
資料の準備 NotebookLMに生成集約する
使う生成AI
- NotebookLM
- Gemini
- Claude
使うアプリ
- Google スライド
- Google Keep
- Google ドキュメント
- YouTube
まず初めに、書きたいものに関係している資料を全部NotebookLM(以後LM)にぶち込みます。
書籍の場合は、OCRがかかって文字データ付きの書類をLM はPDF を読み込むことができ、文字データが入っている PDF を 文字データとして認識されます。また、本全体が必要な文献ではないこともあるので、自分の語りたいことに関係のある章だけをドキュメントにコピーし、書籍とは別に ノートブック LM に 読み込ませます。これは本丸ごと参照させると必要ではない 情報まで取ってくる可能性があるので 条件に合わせて 本 全体を選ばせる場合と読ませたい 章だけを読ませる 限定的に呼び出す場合に後に区別するためです。
インタビュー動画は、文字起こしのために一度YouTubeにアップして字幕を自動生成し文字データをダウンロード、このテキストデータをLMに入れます。
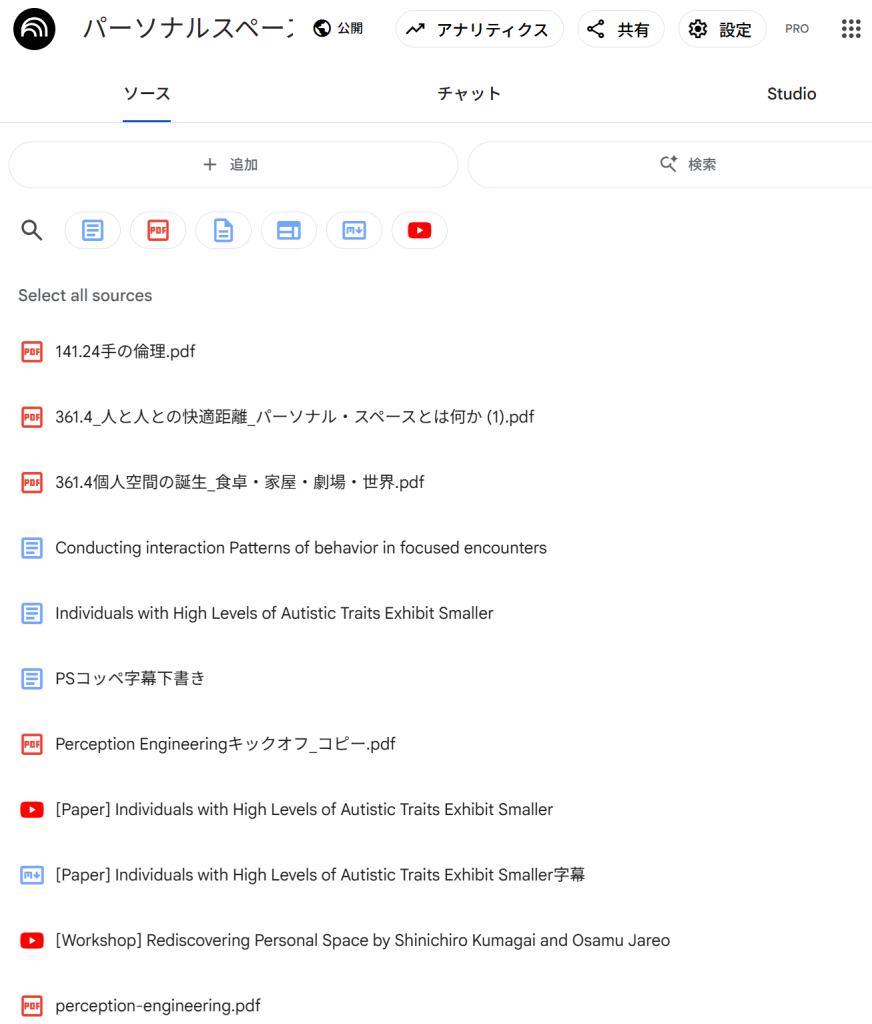
2. 全体の概要と章立てを作成する
ソースをすべてLMにアップロードしたところで、全体の概要文と章立てをLMに作らせます。これは素案生成です
その次は、生成された章ごとにキーワードを箇条書きにしたものをまとめていきます。全部AIにやらせると偏りが出るので、ある程度自分で選別します。私の場合は、それをさらにスライドに貼っています。理由は、この次に出てきまが、ブレインストーミングをする際に話題のきっかけになるキーワード集と同じ役割です。
3. 音声入力で即興的に語る草案作成
次に、この章立てとキーワードを見ながら即興的に喋って、音声文字入力でどんどん入力していきます。この時、テキストファイルよりもスライドの方がサクサク進めるし、写真や動画をどんどん貼り込めるので便利です。音声入力はWindows 11 PCでも行えますが(Macのことはよくわかりません)、Androidの方が調子が良いです。私の場合はKeepにとにかくどんどん入力します。誤入力はややあるのでこれは手入力で直します。
サポート AI かっこ 仮 のコッペ です 今回はパーソナルスペースを使ったメディアアートのワークショップの紹介をいたします こちら 1917年に山口情報芸術センターで行われた パーセプション エンジニアリング キックオフ という イベントの中で行われたワークショップなんですが ダンサー振付家の砂連尾理さんと小児科で 当事者研究でも有名な熊谷真一朗先生と共同では Y カムインターラボが共同で行ったプロジェクトです パーソナルスペースって言うと私たちの見えないね 縄張り みたいな感じで自分の比較的 前方に広がっているんですけれども そのここから私 スペースは私ですよ っていう境界線のところをね 表している表現 なんですけど 日本人はアメリカ人に比べて広いとか言われますよね そういう あのそういった 個人が シチュエーションや文化によっても変わるんですけど個人が所有している空間 縄張り みたいなものがパーソナルスペースと言います これをね モーションキャプチャーのシステムなどを使って 可視化してすることでどんな新しいコミュニケーションが生まれるかな っていうのに注目したワークショップなんてです
4. AIで草案内容を整理する
この文字起こしした文章を、私の場合はGemini、Claude、ChatGPTの3者にお願いします(この時はLMには入れません)。AIに持って行って、概要を整理させます。この好き放題語った内容が論文の骨格になります。ある程度 丁寧にまとめておく方が良いでしょう。整理させたり、要点だけを抽出させたりすると、自分が何を意図したかったのか、自分が思っていることがちゃんと書かれていないケース、資料的に揃えが甘かった箇所などが分かってきたりと、客観的に内容を掴むことができます。
ここでまとまった内容が論文の骨格になりますので、ドキュメント上で整理していきます。基本的にはここから削っていく方が多いので、無駄に長くても構いません。むしろ、用意した資料と同じぐらい喋りまくるぐらいの方がちょうど良いでしょう。
claudeで校正>>
サポートAI「仮」のコッペです。今回は、パーソナルスペースを使ったメディアアートのワークショップの紹介をいたします。
こちらは2017年に山口情報芸術センターで行われた「パーセプション・エンジニアリング・キックオフ」というイベントの中で行われたワークショップなんですが、ダンサー・振付家の砂連尾理さんと、当事者研究でも有名な熊谷真一朗先生と、YCAMインターラボが共同で行ったプロジェクトです。
パーソナルスペースというと、私たちの目には見えない「縄張り」みたいな感じで、自分の比較的前方に広がっているんですけれども、「ここから私の空間ですよ」という境界線のところを表している表現なんです。日本人はアメリカ人に比べてパーソナルスペースが広いとか言われますよね。そういった個人が所有している空間、つまり「縄張り」みたいなものがパーソナルスペースと言います。このパーソナルスペースはシチュエーションや文化によっても変わるんですけれども、モーションキャプチャーのシステムなどを使って可視化することで、どんな新しいコミュニケーションが生まれるかな、というのに注目したワークショップなんです。
ある程度進めると、不足資料が見つかったりするので、資料をまたどんどん調べてLMに追加していきます。
資料が揃ったら、先ほどの草案ドキュメントも読み込ませて、LMのプロンプトには「草案ドキュメントをベースに論文発表のための台本を構築して」とお願いします。ここでチャプタータイトルが重要です。チャプタータイトルは後々まで全体の構造のアンカーとしての働きがあります。後からチャプタータイトルを変えたり増やしてもても良いのですが、とりあえず骨格となるアンカーとなるチャプターは決めておきましょう。またレポートの生成であれば この段階で「草案をベースにレポート作成。ソースだけでなくインターネットの情報も参照…」とお願いし最終の追い込みにかかっても大丈夫でしょう。
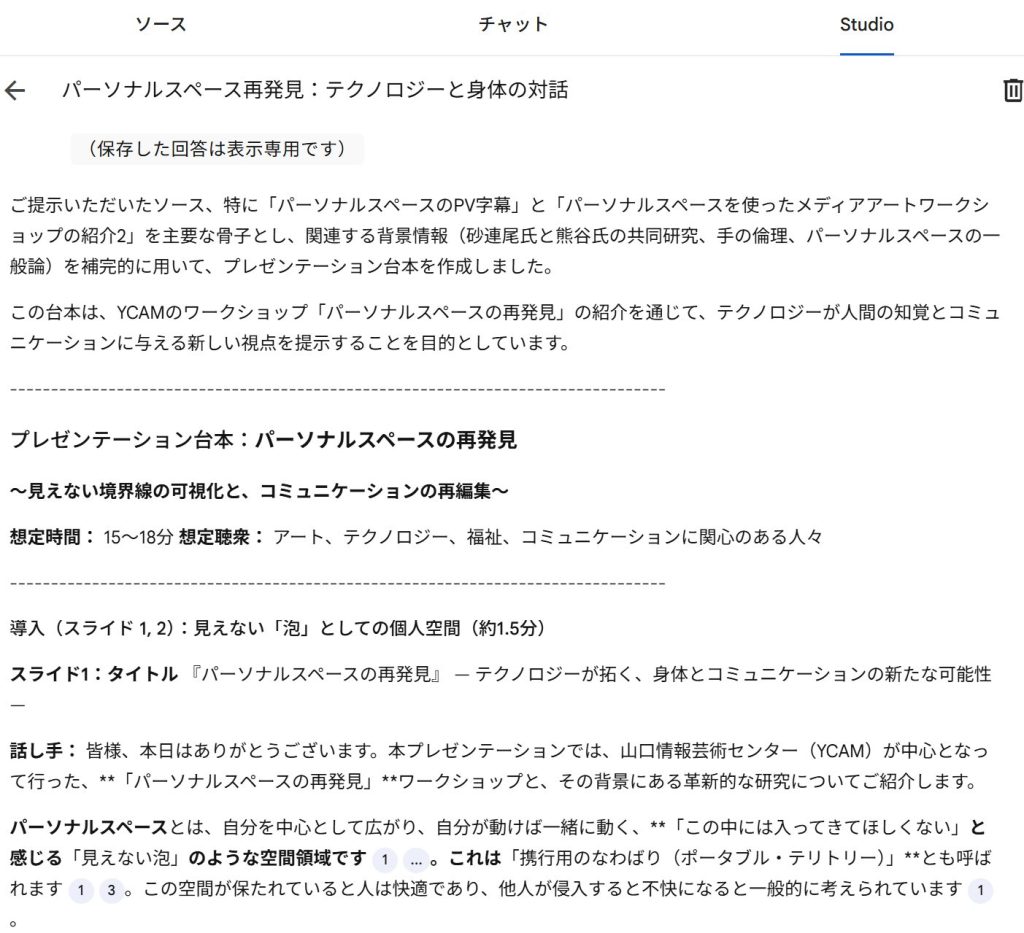
6. 動画作成と録音の繰り返し
ここで出てきた台本を、新しく用意したGoogleスライドに貼っていきます。私の場合は、昨年まではドキュメントを仕上げてから動画を作っていましたが、最近はYouTube動画制作の公開ペースを早くしたかったりで、先に動画を作ってしまうという方法でこの1年はやってきています。ですから、今度は動画用に作成するために、動画用台本としてスライドに原稿をどんどん貼っていきます。また方向性を絞るためにもこの段階で、LMに音声やプレゼン動画もを生成してもらいました。そのままはほとんど使えないのですが、少し異なった 論考を見るのは本編を作る上で 参考になります。この時のスライドの章立てが全体の流れに大きく関わりますし、内容を削っていく時に重要となります。なぜならば、結局気持ちよく喋れたことが自分が考えたことであり、AIが勝手に適当に辻褄を合わせたものは内容が薄くなってしまうので、この辺は気をつけます。
論文作成では複数の論理層を織り込むことが求められます。しかし、生成AIによる作文は、このレイヤー(階層構造)を持たないため、複雑に編み込まれた文章を生成することができません。すべての言葉が1つの皿の上に平坦に並んでしまうのです。
したがって、複雑な文章を構築するには、章ごと、あるいは皿ごとに内容を分け、コース料理のように組み立てる必要があります。先ほど「章立てがアンカーになる」と述べたのは、段階的な積み重ねによって複雑な文章を構築する方法だからです。つまり、作者がAIにレイヤーを意識させるのではなく、うまくレイヤーが形成されるよう、段階的に積み重ねることが重要です。
私の場合は、とにかく頭から最後まで喋り続けて、最後までうまく喋り切れるまで何度でも録音を繰り返します。人によっては細かく台本を区切って録音すると思いますが、私の場合はそんなに器用ではないので、言葉が詰まっるのは良いのですが、棒読みになったり話すまえに「えー」という音が多い場合は言葉が体に腹に落ちていないということなので、スルスルと喋れるようになるまでとにかく頭から繰り返します。これを何回かやっているうちに、もう変わらない、スルスル話せたという部分が出てきますので、そこはキープして、うまく話せない、いつもの話が変わってしまう箇所は、納得がいってないということなので、資料を充填し、論考の道筋を補正して、スルスル 話せるようになるまで繰り返し録音します。
今回の章立て構造は以下なります
- イントロダクション
- 人物紹介およびポストモダンを定義
- 前作の「超連結クリエイション」から「手の倫理」文中「距離りの逆説」の理論へ
- パーソナルスーペースの計測とその意味
- ワークショップの組み立て
- 砂連尾氏のダンス的意義
- まとめと考察
という流れがアンカーです。
煮詰まってきたら 音声生成 動画生成を行って現時点でなら AI 流まとめも参考になります。
録音が完成したら音声を編集し、いわゆる登壇 スピーチのようなものを作ります。さらに先に作ったスライドの画像なども貼っていき 1本の動画にまとめて行きます。ここから先は映像制作になるのでの細かなことは割愛します。動画が完成しましたらYouTubeにアップして普通なら 公開しますが、今回の記事は 論文の作り方なので この続きがあります。YouTube自動字幕 生成をさせ文字データをダウンロードします。自動で字幕化します。このデータは 論文の骨核となる文章となります。
7. 字幕データから論文を構築する
自動で字幕化された音声文字データ(骨核データ)をまたLMに突っ込みます。今度はプロンプトに「字幕データをベースに論文を構築してください」と書くと、これまでちぐはぐだった内容がかなりガッチリした形で文章化されます。若干思っている内容と違っていたり、強調する場所が変わっていたりすることが起きるので、チャットで何度も注文を出して思った通りの内容に変えていきます。この時にも、本からの抜粋を強調したい場合は、書籍の全体ではなく部分抜きの資料の方をプロンプトに直接指示して範囲を指定し、「この部分の引用を挿入してください」といったプロンプトを書くことで、理論をぶれないようにします。
タイトル案もここから生成します。
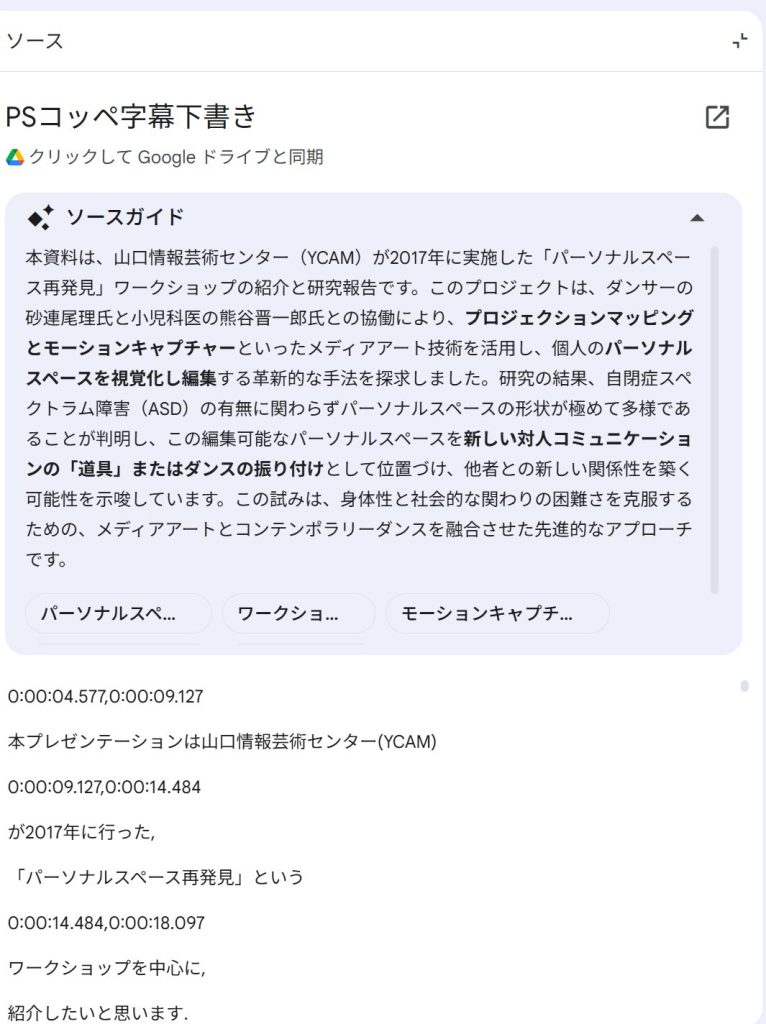
8. 結論部分の必殺技
最後、結論部分ですが、喋っている時も喋り用の台本でも文章でも、やはり結論の部分はかっこよく締めくくりたいと思うので、なかなかいつも苦戦して、時間がかかっている間に締め切りが来たりもします。私流の必殺技をお教えします。結論として用意させた文章の助詞であるとか、細かくしている部分を全部切って、送り仮名付き漢詩のような状態にまで文章を縮めます。これは手作業で行います。これを行った上でプロンプトで「この詩を読みやすい文章に変換してください」とお願いすると、重要単語が確実に使われつつ適当な文章に構築してくれるので、言いたいことがぶれにくくなります。生成A がない昔は英語翻訳してから日本語翻訳に戻したりしていました(自分癖で使ってしまう言い回しや一般的ではない単語が慣らされます)が、こちらの方が綺麗な文章になることが分かりました。結論では複雑な内容をシンプルに簡潔に述べる必要があるので このようなシチュエーションでは役に立ちます。
第一段階 音声から文字入力
このような意味でいわゆる 舞台でのダンスという枠組みから離れ ここが持って日常的な動きの中から自分たちで物語を組み立て それがさらに発展的に 関係性を結ぶことで動きが進化 進化 拡張していくというプロセスは まさに未来のダンスの姿であり 新しい切り口であるという風にいるのではないでしょうか そして 社会 パーソナルスペース研究 対人コミュニケーション研究の方から見ても 実際 学術的に何かを証明するということではないのですが 新しい道具を導入することによって私たちは ビデオチャットなどを使うことで 新しい 対人関係を手に入れてきましたが 別の方法で 対人 道具を導入することで全く新しいあのこれまでとは異なる対人関係を築くことができるかもしれないということを示唆しているとも言えます これを持って 発表を終わりたいと思います。
第二段階 余分な文字を消去
舞台でのダンスから離れ
日常 動き 自分たち 物語組み立て 発展
関係 結ぶ 動きが進化 拡張
未来のダンスの姿で 新しい切り口
社会 パーソナルスペース研究 対人コミュニケーション研究学術 証明する
新しい道具を導入する 私たちは ビデオチャットなどを使う
新しい 対人関係を手に入れ 別の方法
対人 道具を導入 異なる対人関係を築く
これを持って 発表を終わりたいと思います。第三段階 AIで生成
claudeでの変換
舞台でのダンスから離れ、日常の動きや自分たちの関係性の中に物語を組み立てることで、ダンスは進化し拡張していきます。未来のダンスの新しい姿は、社会やパーソナルスペース研究、対人コミュニケーション研究という学術的な視点から証明されるものになるでしょう。
私たちは新しい道具を導入することで、これまでとは異なる対人関係を手に入れることができます。ビデオチャットなどのデジタルツールを使うことで、別の方法による新しい対人関係が築かれ、道具の選択によってさらに異なる対人関係も構築できるようになります。 これらのことをお伝えして、発表を終わりたいと思います。
geminiでの変換
従来の舞台芸術としてのダンスから離れ、私たちは日常の動きを新たな表現の核として捉えます。
自分たちで物語を組み立て、関係性を発展的に結ぶことで、動きが進化・拡張していくプロセスこそが、「未来のダンス」の新しい姿であり、切り口です。
これは、単なる芸術論に留まりません。私たちは、パーソナルスペース研究や対人コミュニケーション研究といった学術的な知見を基盤とし、新しい道具(テクノロジー)の導入によって、社会に貢献する可能性を探っています。
かつてビデオチャットが新しい対人関係をもたらしたように、別の方法、すなわち身体に根ざした新しい対人道具を導入することで、これまでとは根本的に異なる、新しい対人関係を築くことができるかもしれません。
この提案をもって、私の発表を終わりにしたいと思います。
notebooklmでの変換
私たちは、舞台でのダンスから離れ、日常の動きの中に立ち戻り、自分たちの身体を通して物語を組み立て、発展させることに注目します。
これは、単に表現するだけでなく、「表現しないと生き延びられない」という状況にある人々(障害を持つ人々)が、世の中を変えうるような、まだ表現未満の経験や、表現として流通していない経験を生み出す起爆剤として、障害分野がアートに提供できる切実さから来ています。
ダンサーと研究者の共同作業を通じて、関係を結ぶことで動きが進化、拡張していく様子が観察されています。例えば、砂連尾理氏と熊谷晋一朗氏の「超連結クリエーション」では、介助者と被介助者という一方的な関係ではなく、二人がお互いに支え合い、新しい動きが生まれる様子が捉えられました。この試みは、未来のダンスの姿で、新しい切り口を提供するものです。
学術的には、社会や対人コミュニケーションの理解を深めるために、パーソナルスペース研究の知見が利用されました。これは、自閉症スペクトラム傾向の方々においてパーソナルスペースの形状や距離がコミュニケーションの妨げになっている可能性を探る研究課題です。この種の学術的アプローチでは、パーソナルスペースの形状やコミュニケーション中の変化を測定しようとしました。
また、私たちは新しい道具を導入し、異なる対人関係を築くための別の方法を模索します。例えば、ビデオチャットのようなデジタルツール(ご提示のキーワードより)も考えられますが、本研究に関連する例として、二人の間で棒という対人 道具を導入した実験が行われました。
この道具を介したやり取りは、物理的な接触を避けつつも、距離をとることによって、かえって中に入ることができたという逆説的な現象をもたらしました。棒の使用によって、手の表面の奥にある、相手の関わろうとする気持ちや微妙な振動といった、視覚では分からない情報が伝わり、視覚による理解を裏切る新しい対人関係を手に入れることができたのです。
これを持って、発表を終わりたいと思います。
まとめ
以上の方法を使えば、それっぽい論文は書くことができます。やはりコツとしては、AIは多重構造を理化してくれないので細かく章立てすること。LM野芥港として、自分が用意した資料に引っ張られやすく、言い切りやすい文章を引用する傾向がありますので、書籍も必要部分は別ドキュメントとして逃がしておくこと、チャットで生成た使えるセンテンスはメモ保存だけではく、メモからソース変換をして、ソースを充実させた方が良いようです。チャットでいろいろな方法で質問すること、プロンプトでしつこく指定することが重要なようです。
覚えておこう:LMのチャット内容はそのまだとAI学習されません。メモに保存してもAI学習されません。メモ保存後、ソースに保存ボタンで保存しないとソースデータにはなりません。お気に入りは豆にソースに変換しましょう。