今回のシンポジウムのテーマは「ヴァーチャル」で、一見すると「ヴァーチャルリアリティ」と誤解を招きそうなタイトルですが、実際の内容は哲学者ジル・ドゥルーズが用いた意味での「ヴァーチャル」に基づいていました。そのため、議論の中心は工学的なバーチャルリアリティやメタバースではなく、哲学的および芸術的な視点でした。このブログはつらつらとその時思ったことを書き留めています。
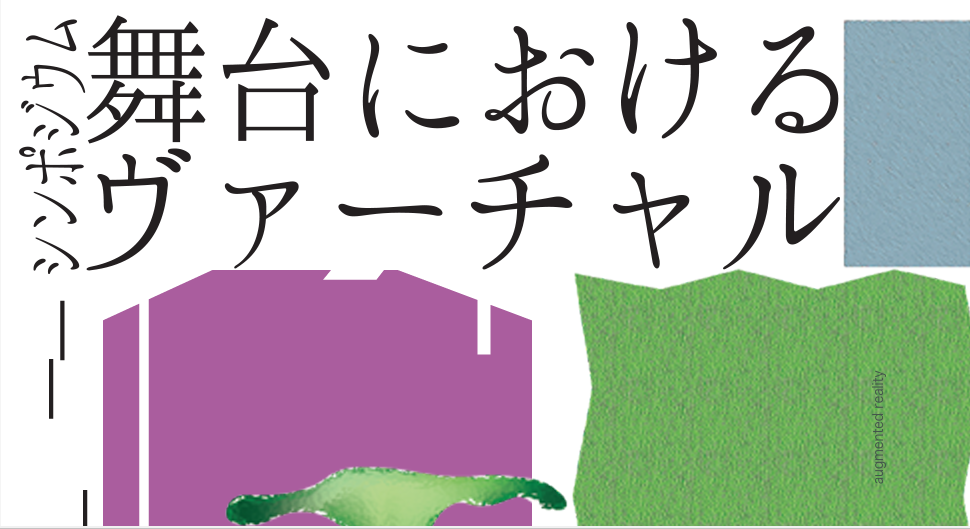
松田正孝氏による「母の死を上演する試み」や、パネルディスカッションでは、演劇、能楽を題材にした表現など、死者との対話や「不在」を舞台芸術に取り入れる試みも紹介されました。この「不在」という概念が、シンポジウムでは「ヴァーチャル」と呼ばれていました。
砂連尾理は「逆さまメガネ」通じて何をしようとしていたのか?
わざわざ東京まで行った理由は、砂連尾理さんが「逆さまメガネ」を用いたプレゼンテーションワークショップを実演すると聞いたからです。このプレゼンテーションは普段と異なる身体点を取り入れることで、身体感覚の反省的にとらえることが目的とされています。
実演では、参加者が2人1組となり、逆さまメガネを装着してキャッチボールやプリンを食べさせ合うパフォーマンスを行いました。逆さまメガネを装着すると左右や上下が反転して見えるため、動きが不安定になり、普段の動作が大きく制約されます。この体験は、コンピューターの画面を傾けた際にマウス操作が難しくなる感覚に似ています。
さらに、ダンス未経験の観客が逆さまメガネを装着し、過去にシンガポールで砂連尾さんが行ったパフォーマンス記録を視聴。その内容を即興で再現する試みも行われました。その後、砂連尾さん自身がその再現された動きをトレースするという形で、視覚の変化が身体に及ぼす影響を探求しました。
砂連尾さんのプレゼンテーションパフォーマンスにはいくつかの問題点があります。その一つは、逆さまメガネの使用に関する問題で、逆さまメガネを導入した最大の理由は、普段慣れ親しんだ身体に疑問を持つことで、自分のこれまでの動きを反省的に捉えることにありました。
しかし、逆さまメガネは使えば使うほど慣れていくもので、1週間もつけていると普段と変わらない視覚になると言われています。つまり、練習すればするほど慣れてしまい、もともとの主題から外れてしまうという問題があります。したがって、このように慣れてしまうメディアを使って、今ここにいない人物と踊ることを追体験するということには限界があります。私が砂連尾さんに提案したのは、相手の目線になって自分のパフォーマンスを見るという、バレエスタジオにおける鏡のような視点を取り入れることでした。これは、VRやXRといったメディアを活用し、自分の姿を外側から客観的に見る方が、本来の主題により適しているのではないかということです。実際時間的制約や立教大学の心理学科のデジタル化に取り組み具合にもよるものなので今回は、伝統的な実験装置でのプレゼンテーションに落ち着いたといったところです。
想像以上の効果があったかどうかはさておき、新しい不在へと取り組みとうのは評価すべき取り組みです。VRでの表現に限界を感じていると話す劇場系のプロデューサーにはこういった視点も興味を持って取り組んでもらいたいものです。
自分が過去に取り組んだ視点の他者化から再身体化するワークショップとその考察がすでにありますので、興味がある方は参照ください。
多様体の問題
ここで横山太郎先生が当日説明していた、ドゥルーズの「ヴァーチャル/アクチュアル」に関する基本的な定義を補足します:
- possible(可能なもの) – real(現実的なもの)
- possible は real に似ているが、実在していないだけである。
- realization(実現)では本質的に新しいことは起きない。
- virtual(潜勢的なもの) – actual(現勢的なもの)
- どちらも real の一部だが、両者は似ていない。
- virtual は「種」や「問い」、actual は「花」や「答え」を指す。
- actualization(現勢化)は「解決」を意味し、新しい出来事の発生を伴う(花や木の形があらかじめ決まっていないように)。
後半のシンポジウムで議論されました、ヴァーチャリティとアクチュアリティそれに続いてドゥルーズが使用した多様体という言葉がに引っかかりを感じました。この「多様体」(マニフォールド)は、そもそも数学者リーマンが提唱した概念であり、本来は感覚表象的な空間直観に依存しない空問概念で、離散多様体と連続多様体の2種類に分類されます。特にリーマン多様体は、高次元の対象を理解・計算するために、より低次元の空間、例えば2次元平面に射影するという考え方を基礎としています。
現在、多様体という概念は数学における厳密な定義に加え、物理学、特に相対性理論での応用、そして哲学、特にドゥルーズによる概念的使用など、様々な分野で使用されています。しかし、特に人文系の議論において「多様体」という用語が、本来のリーマンによる数学的定義から大きく離れて使用されている点は看過できない問題をはらんでいます。単にヴァーチャルな概念の集合を指す言葉であったり、思考的な高揚感などで安易に使用されている傾向が見られるのです。
このような状況を踏まえると、多様体という概念については、数学的定義と哲学的解釈の関係性の明確化、各分野における使用法の整理が求められます。
私の「多様体」の解釈は、特に離散多様体について、キュビスムの手法で自分の顔を描くことに例えることができます。立体の顔を複数の角度から解体して要素を再構築し、世界地図のように展開面としてかくことです。外から観測するのではなく、観測者が自分であることが重要です。誰もが鏡を見たり、触ってみたりして、自分の顔がどの様なものか知っているわけです。
連続多様体については、これらの構造が入れ子状に複数存在する状態として理解できます。数学者の岡潔の研究内容は全く理解できていませんが、かなり高次元での次元変換を用いた計算を行っていたことは確かです。このように、ある次元の対象を別の次元に射影するという点で、現代のAIにおけるクラスタリングで行われる次元圧縮と本質的に類似していると考えられます。数学的には、物理学における空間圧縮と情報処理における次元圧縮は異なる概念として扱われているようですが、いずれも隣接する次元の「影」を段階的に捉えていく作業である点で、根本的には同じ原理に基づいていると私には思われます。
カンディンスキーと多様体
このように考えると、多様体という概念はさほど大げさなものではないと思われます。むしろ、この考察から自分がその時勝手に導かれた興味深い発見として、カンディンスキーが提唱する「基礎平面」という概念が多様体と類似した構造を持っていることが挙げられます。
カンディンスキーにとって、点や線は内的な精神世界から生まれるものであり、それを基礎平面に射影するという考え方を持っていました。これは、作曲家が心に浮かんだイメージを楽譜として書き記すプロセスと同様です。実際にカンディンスキーは、絵画と作曲を頻繁に比較していました。
数学における多様体との本質的な違いは、対象とする空間の性質にあります。数学では物理的な空間を扱い、直接捉えられない形状を2次元平面というプラットフォームに射影することで測定可能にします。一方、カンディンスキーの場合は、イマジネーションという内的空間を扱っているという点で異なっています。ただし、どちらも「捉えがたいものを特定の平面に射影して理解可能にする」という共通の方法論を持っているといえるでしょう。
参考絵リンク> 曲面から導く多様体の基礎